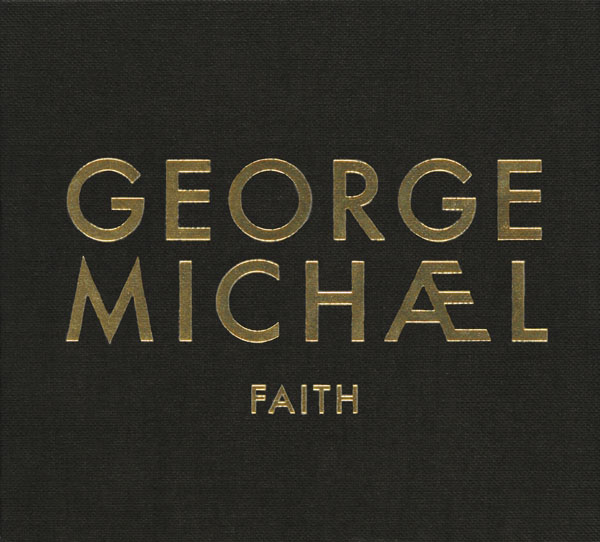『FAITH』ライナーノーツ
text西寺郷太(ノーナリーヴス)
(本稿は2011年2月に発売された『FAITH』デラックス・コレクターズ・エディションのライナーノーツを筆者の許可を得て転載したものです)
群雄割拠の'80年代、KlNG OF POP = マイケル・ジャクソンに次ぐ 「8曲」 の全米No.1シングルを獲得した男、ジョージ・マイケル。87年秋、同時期に発売され、共に世界中で驚異的なヒット作となった『BAD』と『FAITH』は、黒人・白人それぞれの側から「ジャンルの壁」を壊した。
若き天才の信念(FAITH)が奏でた、音楽の魔法がここにある!
《FAITH》とは?
1987年10月30日にリリースされた《FAITH》は、前年にポップ・ミュージック界の頂点を極めた人気デュオ「ワム!」を解散させたばかり、当時24歳のジョージ・マイケルがリリースした、彼にとってはじめてのソロ・アルバムである。本作のレコーディングは、主にデンマークのP.U.K.スタジオ(本国イギリスの高い税率から逃れるため)と、ロンドンのサーム・ウェスト・スタジオで行われた。ここでジョージは当時最先端の録音機器シンクラヴィア9600(日本円で約1億円)を導入し、彼にとってはじめてのデジタル・レコーディングにトライしている。
本作は、6曲の全米トップ・ファイヴ・シングル(4曲の全米ナンバー・ワン・シングル〈フェイス〉〈ファーザー・フィギュア〉〈ワン・モア・トライ〉〈モンキー〉を含む)を生み出し、12週間全米アルバム・チャートの首位に輝く大ヒット作となった。10位以内にもトータルで51週間とどまった結果、本作《FAITH》と、タイトル曲〈フェイス〉はそれぞれ、88年度ビルボード年間チャートでアルバム、シングルともに首位を獲得するという快挙を達成。2011年1月現在までに、全世界で2000枚以上のビッグ・セールスを記録している。
ワム!と、本作での歴史的成功によって、ジョージは「80年代、全米ナンバー・ワン・シングル最多保持者」のマイケル・ジャクソン(9曲)に次ぐ、第2位の座(8曲/フィル・コリンズと同率)を獲得するほどの地位を手に入れる。まさに名実共に「80年代を代表するアーティスト」となったのである。
《FAITH》への賞賛の声は、ファンからの信頼と支持を意味するその圧倒的なセールスのみにとどまらなかった。本作は、89年2月22日に発表された「第31回グラミー賞式典」において、名誉ある「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞する。スティングの《ナッシング・ライク・ザ・サン》の他、スティーヴ・ウィンウッド、ボビー・マクファーリン、トレイシー・チャップマンという「玄人受けする」面々の傑作群を抑えての「アルバム・オブ・ザ・イヤー」の獲得は、それまでジョージの若さとルックスの良さによる先入観から、彼を実力のない「アイドル」と見なし、ワム!時代、彼ら自身の戦略的に自らのアイドル性を利用した悪ふざけ(ライヴ中、ショート・パンツにバトミントンのシャトル・コックを忍び込ませ女の子達の嬌声を浴びるなど・笑)に冷笑を浴びせた音楽業界人・評論家筋からの高い評価も得たことをも意味した。
シンガー、パフォーマーとしてではない、彼のソングライター、プロデューサーとしてのキャリアもこれ以上ない領域に達する。ソロ・アーティストが、自身による単独プロデュース作でグラミー賞「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を手にしたのは、70年代のスティーヴィー・ワンダー以来のことだった。
ジョージ・マイケル、《FAITH》に至るまでの歴史とその特異性
ジョージ・マイケル、本名ジョルジオス・キリアコス・パネイトゥーは、1963年6月25日、ロンドン北部フィンチャレー地区で暮らす父ジャックと母レズリーとの間の第三子、長男として生まれている。
彼の父親ジャックは、50年代初頭にキプロス島出身のギリシャ系労働者としてイギリスへと渡ってきた移民第一世代であった。父ジャックはウェイターとして過酷な労働を重ねながら、キプロス島に暮らす親・兄弟姉妹に仕送りを続け、最終的には6人の兄弟姉妹のほとんどをイギリスに呼び寄せ、後にはレストラン経営者となる「一族の英雄」である。
75年9月、12歳になったジョルジオス(ジョージ)は、引っ越し先のブッシー・ミーズ中学に2年生から編入。そこで、後にワム!のギタリストとなるクラスの人気者アンドリュー・リッジリーと出会う。「有名になるため」にサッカー選手か、ポップ・スターになりたいという動機を持ち、すでにバンドも結成していたアンドリューの陽気なパーソナリティは、当時太っていて牛乳瓶の底のような眼鏡をかけていた繊細なジョルジオス少年の人生を変えた。偶然にもギリシャ人の父を持つジョージと、地中海の同じ一角であるエジプト、アレクサンドリア出身の父を持つアンドリューとは移民二世としてのアイデンティティも共有していた。
ジョージとアンドリューは14歳で当時一世を風靡したディスコ映画『サタデー・ナイト・フィーヴァー』に衝撃を受けたり、その後巻き起こったツー・トーンのブームに夢中になったりしながら、79年夏、幼馴染みのデヴィッド・オースティン(本作収録〈ルック・アット・ユア・ハンズ〉【M7】の共作者)を含む数人の仲間とともにスカ・バンド「ジ・エグゼクティヴ」を結成する。スタジオを借り、16トラックのレコーダーでデモ・テープ作りにトライした彼らだったが、レコード・レーベルに送りつけても良い反応が返って来ることはなかった。
現実の波を、そのひたむきな労働で乗り切り、家族を養ってきたジョージの父ジャックにとって、青年へと成長した自らの息子がいまだ「ミュージシャンになる」などと浮ついた夢を語り続けることを許すことは出来なかった。車の中でジョージから当時レコード会社に持ち込んでいたデモ・テープを聴かされたジャックは、息子を諦めさせるためにこう言ったという。
「17歳くらいの子供はみんなポップ・スターになりたがるものなんだ」
「違うね、父さん」ジョージは答えた。
「みんなポップ・スターになりたがるのは12歳までだよ」
僕がジョージ・マイケルを「とてつもない天才」だと思うのは、この父親とのエピソードが示すように、彼がそのあまりにも早熟な才能と未曾有の成功からは想像出来ないほど、デビュー前まで「至って普通」の家庭環境・状況でもがいていた青年だからである。
ジョージは、例えばマイケル・ジャクソンのようにロー・ティーンの時代からメディアの注目を浴びていたり、家族の「夢」の体現者として重圧を受けながらショー・ビジネスの世界を突き進んでいたわけではない。彼のそばにはマイケルに様々な技術を伝えた、ギャンブル&ハフやクインシー・ジョーンズという偉大なプロデューサー達はいなかった。
曲芸的な楽器演奏のスキルを持ち、複数のレーベルの争奪戦の中で破格の契約を結ぶことが出来たプリンスのような「天性のマルチ・ミュージシャン」でもない。マドンナのように、優秀なプロデューサーやソングライターを見抜く審美眼を持ち、成長を階段を上りながらパートナーを時代ごとに乗り換えていったわけでもない。
ジョージは普通に黒人音楽のマニアで、映画館でバイトをし、幼馴染みとバンドを組み、父親からは音楽の道に進むことを執拗なまでに反対されていた。失業保険をもらい、そのお金でディスコに踊りに行く毎日、レコード会社からデモテープは門前払いを受けて・・・。アイディアはあるものの楽器の演奏は拙い・・・。
つまり19歳までのジョージは社会的には「なんのへんてつもない若者」であった。しかし、そんな出発点から「奇跡」が始まったのである。彼は「笑顔と元気が持ち味」の相棒アンドリュー・リッジリーとともに、はじめてのレコード・リリースからわずか3年半で世界のポップ地図を塗り替えてゆくのだ。
正規の音楽教育も受けず、プロとしてのトレーニングや「下積み」もないままにデビューしたジョージだったが、その類いまれなる音楽的頭脳を持ってあっという間にスタジオでの音楽制作をコントロールする術を身につける。
20歳の夏に発売されたファースト・アルバム《ファンタスティック》の世界的な成功の後、21歳で〈ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ〉〈ケアレス・ウィスパー〉〈恋のかけひき(エヴリシング・シー・ウォンツ)〉という3曲の全米ナンバーワン・ヒットを手中に収めただけでなく、84年のクリスマス・シーズンには、世紀のエヴァーグリーン〈ラスト・クリスマス〉も発表。イギリスのアーティスト達がアフリカの飢餓救済のために立ち上がったプロジェクト、バンド・エイドの〈ドゥ・ゼイ・ノウ・イッツ・クリスマス?〉にもメイン・シンガーのひとりとして参加。この年は、ジョージの歌った2曲のクリスマス・ソングがチャート首位と2位を占めた。
極めつけは、ジョージのソロ作品として発表された〈ケアレス・ウィスパー〉が、85年度ビルボード全米年間シングル・チャートで首位を獲得したことだ。まさに、怒濤の進撃・・・。しかし、「若きアイドル」としてのあまりにも巨大な成功が呼んできたタブロイドからの容赦ない攻撃と誤解、要求される楽曲のイメージとの葛藤は、純粋に「音楽家」として名を残したいと願っていたジョージにとって心地よいものではなかった。
マネージャー、サイモン・ネピア・ベルはこのように語る。
「ワム!はアンドリューのイメージなんだ。ジョージの方が彼を模倣していたんだ。酷似しすぎたので、アンドリューは影が薄いと言われたが、「ワム!」はアンドリューがふたりいたようなものだ。やがてジョージは本当の自分に目覚めて、作曲やプロデュースをひとりで手掛け始めた。気のいいアンドリューは好きなようにさせてたよ」
《FAITH》発表前夜
86年、ジョージはグループ名義で作品を発表することに限界を感じ、絶頂を迎えていたワム!の解散を決める。そして、23歳の誕生日を迎えたばかりの86年6月28日、ロンドン・ウェンブリー・スタジアムで行われたワム!解散コンサート「ザ・ファイナル」は、100万人の応募者の中からチケットを獲得した彼らとの別れを惜しむ7万2000人の観衆の目前で盛大に行われた。
ワム!解散後、しばらくの休息と、アルコールとドラッグに溺れた絶望の日々を挟んで、ジョージは活動を再開する。86年12月、ジョージが彼の憧れであった「ソウルの女王」アレサ・フランクリン側からの呼びかけに応えてデトロイトでのレコーディングに参加、当時「旬」な存在のナラダ・マイケル・ウォルデンがプロデュースを手掛けて完成した〈愛のおとずれ(アイ・ニュー・ユー・ワー・ウェイティング・フォー・ミー)〉は、それまで基本的に作詞・作曲・プロデュースのすべてを手掛けてきたジョージが珍しく「純粋なるシンガー」として参加した作品である。
87年2月にリリースされた〈愛のおとずれ〉は、4月18日付で全米ナンバー・ワン・ヒットを記録。ジョージにとってワム!時代から数えて4曲目、アレサにとっては67年の〈リスペクト〉以来20年ぶりの首位獲得曲となった。
ジョージは彼の自伝「裸のジョージ・マイケル / BARE」で、共同著者のトニー・パースンズにこのように回想している。
「アレサ・フランクリンとの仕事の、特にアメリカでの成功は、そこには本気で立ち向かっていくべきものがあるんだって気づかせてくれた。僕は、マドンナ、プリンス、ジャクソンと同じラインに入らなくてはならないのがわかってた・・・。それは、僕がワム!時代にイギリスで競い合ってたフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドや、スパンダー・バレエ、ボーイ・ジョージのカルチャー・クラブ、デュラン・デュランといった人たちの多くが低迷してるか、駄目になったかのどっちかだったという事実にも関係していた。誰が自分の競争相手か見極めなくちゃいけない。競争がもはや挑戦のし甲斐のないものになってしまったのなら、別の競争相手を見つけなくちゃいけない。自分の作品があんまり良くないんじゃないかって心配したことはないけど、自分のパーソナリティはあんまり新鮮じゃないんじゃないかって心配した。自分にアメリカのスーパースターのような資質があるかどうか、その頃はよくわからなかった」
ワム!の喪失に打ちひしがれ、ジョージの新作発表を心待ちにしていた世界中のファンの度肝を抜いたのが、87年6月に発表された《FAITH》からの先行シングルでエディ・マーフィ主演の映画『ビバリーヒルズ・コップ2』のサウンドトラック・アルバムにも収録された〈アイ・ウォント・ユア・セックス〉【M3】である。ジョージがこの曲に込めたメッセージは、ミュージック・ビデオにおいて彼が当時の恋人であるキャシー・ジュングの背中に「MONOGAMY(一夫一婦主義/一対一)を追求しろ」と口紅で書いた通り、「本当に愛する相手ひとりと愛し合うこと」を追求するべきだ、というものであったが、センセーショナルなタイトル、歌詞は物議を醸し、英国BBC 他、各種メディアで放送禁止の憂き目を見る。
〈アイ・ウォント・ユア・セックス〉は、論争を呼びながらも全米ポップ・チャート2位まで駆け上がる大ヒットを記録した(セールスでは2週連続1位だったが、放送禁止のためラジオでの放送回数がカウントされず2位にとどまってしまう)。
《FAITH》の衝撃
アルバムの予告編となった〈アイ・ウォント・ユア・セックス〉と、カップリング曲〈ハード・デイ〉【M6】が衝撃的だったのは、そのタイトルや歌詞の世界観だけではない。ジョージ自身が「プリンスに影響を受け過ぎた」と後にジョーク混じりに告白するが(おそらく87年初頭にリリースされた〈サイン・オブ・タイムス〉をアイディアの下敷きにしていると思われる)、リズムの隙間をストイックにコントロールしたこれらの楽曲のアレンジメントは、躍動的な60年代・70年代ソウル・ミュージック・リヴァイヴァリストとして知られた「ワム!的な生演奏のサウンド」を予想していた多くのファン達の想像を超えていた。
ワム!時代にも〈エヴリシング・シー・ウォンツ〉〈ラスト・クリスマス〉〈ディファレント・コーナー〉など一部の曲において、自ら一台のシンセサイザーを用いてすべてのサウンドを構築していたジョージであったが、世界中の一流ミュージシャンを集める予算はあったにも関わらず、敢えて〈アイ・ウォント・ユア・セックス〉〈ハード・デイ〉でも、彼自身がすべての楽器を手掛けることを選んだことでそのD.I.Y 指向を明確にしていた。
その選択は功を奏する。アルバム《FAITH》の最大の魅力は、その「セッション・ミュージシャン的な手癖に頼ったなんとなくの流暢さ」の対極にあるような、限りなくパーソナルな(ある種、不器用な)トラックの上を、あまりにもセクシュアルで天才的なジョージのヴォーカルが縦横無尽に弾け飛ぶという「ミスマッチ/せめぎ合い」の中にあるからだ。
87年10月、新生ジョージ・マイケルの登場を高らかに宣言したシングルが、アルバム・タイトル曲の〈フェイス〉【M1】である。50年代から活躍する偉大な黒人ロックンローラー、ボ・ディドリーが流行させたジャイヴ・ビートと、80年代的なチープなドラム・マシーンを組み合わせたフレッシュなサウンドはタイムレスな魅力を放っている。97年のリンプ・ビズキットによるユニークなカヴァーを筆頭に、多数のカヴァー・ヴァージョンが生まれるスタンダードとして今も愛され続けている。
〈アイ・ウォント・ユア・セックス〉と同じく当初はプリンスに影響を受けたミディアム・テンポのダンス・トラックだったとジョージが語る〈ファーザー・フィギュア〉【M2】は、レコーディング中にアクシデントでスネア・ドラムを消したパターンでリズムが再生されたことにピンときたことから、ミステリアスな魅力を持つ最終的なアレンジへと発展していったという。ジョージの音楽や声質がその軸に持つ「オリエンタル(東洋的)な憂い」が全編を潤した類似品なき彼特有のメロディは、ワム!時代の代表曲〈ケアレス・ウィスパー〉や、本作収録の〈ハンド・トゥ・マウス〉【M6】などに通じるものだ。
イギリスへ移民として渡ってきたジョージの父ジャックの故郷キプロス島はアジア、オリエントの玄関に位置する。我が国でも、ごく初期のワム!時代から複数の日本人シンガーによってカヴァーされヒットするなど、ジョージの生み出すメロディが大衆の熱狂的な支持を受けてきた秘密は、彼の体に半分流れる地中海の「血」、その「オリエンタルな憂い」にこそ隠されているのではないだろうか。
エネルギッシュで宗教的なパワーを持つ全米ナンバー・ワン・ヒット〈ワン・モア・トライ〉【M4】について、ジョージ自身は発表当時このように語っている。
「僕が、ここ5年、10年で書いてきたバラードの最高傑作だ。〈ケアレス・ウィスパー〉は多くの人に愛されているけれど、僕を感情的にはさせないんだ。あの歌は僕自身の人生とは別の物語を歌ってるからね。〈ワン・モア・トライ〉は違う。この歌は僕の心の奥から湧き出てきたものなんだ」
当初はアルバム・タイトルとしてアナウンスされていた〈キッシング・フール〉【M9】は《FAITH》からの最後のシングル・カットとして、全米チャート5位まで上昇したジャズ・スタンダード的な名曲。
センシュアルでダーティな、その吐息に吸い込まれてしまいそうな〈ラスト・リクエスト(アイ・ウォント・ユア・セックス Parts 3)〉【M10】では、ワム!時代の〈ブルー〉を彷彿とさせるデジタル・ビートにのったジョージのヴォーカルが堪能できる。
DISC 2
〈モンキー〉【M8】は、繰り返されるシンプルなメロディとエモーショナルなヴォーカルが印象的なデジタル・ファンク・チューン。シングル・カットの際、ジョージはジャネット・ジャクソン《コントロール》や、ヒューマン・リーグ〈ヒューマン〉などでナンバーワン・プロデューサーとしての地位を確立していたジャム&ルイス(プリンス一派のザ・タイム出身)に声をかけた。
彼らは回想する。
「俺たちがプロデュースしたジャネットのアルバムから、リミックスやライヴ・ヴァージョンをまとめたアルバムを作ることになって、4曲を《モア・コントロール》としてリリースしたんだ。そうしたら、ジョージがその中の〈ナスティ〉のリミックスを本当に気に入ってくれてね。彼が言うにはアルバム・ヴァージョンの〈モンキー〉は、もう少しメロディックに、コードも思い描いていたレヴェルまで到達させたかったけど、制作終盤の〆切に間に合わなかった、完璧に納得は出来ていない状態なんだ、と。で、俺たちに『もし良かったら、〈モンキー〉をプロデュースし直してくれないかな?』って」
ジャム&ルイスは、最初からバック・トラックを作り直し、ジョージもツアー中のハード・スケジュールの間をぬって新たにヴォーカルをレコーディングし直した。旬のサウンドメーカー、ジャム&ルイスがこの時期特有のド派手なリズム・アレンジで新たにまとめた「7" Edit Version」は、リリースされるとチャートを勢い良く駆け上がり、88年8月27日、《FAITH》からの4曲目の全米ナンバー・ワン・ヒットとなった。
DISC 2 に収録された〈フェイス〉(インストゥルメンタル)を聴くと、いかに同曲のバックトラックが、楽器数、音数が少ないシンプルなものかということと、それでいてリズム(スナップ、タンバリン、ハイハット等)の抜き差しや、立体的なミキシングによって、聴く者を飽きさせない効果的な工夫が随所に施されている事に改めて気づく。
〈ファンタジー〉は、《FAITH》に続いて90年にリリースされた《リスン・ウィズアウト・プレジュディス Vol.1》からのシングル〈フリーダム 90〉のカップリング曲。ジョージが発表してきたアップテンポ・ナンバーの中では比較的地味な立場にあったが、2006年から08年の間に行われた、ジョージのデビュー25周年を記念した大規模ツアー「25LIVE」の終盤でセット・リストに組み込まれた。
DISC 2 のハイライトは、スティーヴィー・ワンダーのアルバム《トーキング・ブック》収録曲〈アイ・ビリーヴ〉と、《キー・オブ・ライフ》収録曲〈ある愛の伝説(ラヴズ・イン・ニード・オブ・ラヴ・トゥデイ)〉のライヴ・カヴァー・ヴァージョン2曲だろう。
ジョージは語る。
「スティーヴィーの曲をライヴでカヴァーするのにはそれなりの理由がある。音域、声のレンジが重要なポイントなんだ。彼の曲を4、5曲カヴァーしてるよ。作曲家としても尊敬してるけれど、彼の曲の『キー』が好きなんだ。一昔前の彼の曲は、今の彼の曲よりもっと低くて、僕の声にぴったりあうので、ライヴでも反響が大きいんだよ」
「人種の壁を超える」
本作の持つ大きな意義は、この作品が「人種の壁を越えた」ことにある。《FAITH》は白人アーティストのアルバムが、R&B アルバム・チャートで首位を獲得したはじめての作品となった。そして、ファンからの投票によって受賞作が決定されるアメリカン・ミュージック・アウォードでは、通常は黒人アーティストの作品が選ばれる「ソウル・R&B部門」のフェイヴァリット・アルバムを獲得しただけでなく、ジョージ自身も、マイケル・ジャクソンやボビー・ブラウンを抑えて「フェイヴァリット・ソウル・R&B・アーティスト」に選ばれたのである。
ジョージはインタヴューに、こう答えている。
「長い間、物真似だと言われていたので、これで本物になれたと思った。チャートで一位になるには、大勢の黒人の支持が必要だ。ソウル・シンガーとして認められたと思った。僕は黒人歌手を真似してないし、ソウルが『売り』でもない。レコードが売れた理由は他にあるんだ。例えばバック・コーラスに黒人を起用してるけど、僕の声の方が勝っていたということさ」
しかし、この人種を超えたあまりの成功・賞賛は物議を醸し、同業者からの嫉妬・批判をも呼ぶことになる。自身のアルバム《オール・フォー・ラヴ》で「ソウル・R&B 部門」のフェイヴァリット・アルバムにノミネートされていたたもののジョージに賞を奪われる形になったグラディス・ナイトをはじめ、パブリック・エナミー、スパイク・リー、ディオンヌ・ワーウィックなど黒人アーティスト達からは「なぜわざわざ白人に『黒人音楽』の賞を与えるのか」と抗議の声が挙った。
ジョージは反論する。
「僕がやったのは白人社会のアメリカに黒人音楽を受け入れやすくしたってことなんだ。エルヴィスもそうだった。僕は黒人の真似をしたのではなく、いい音楽を追究したら結果的にそうなったんだ。僕がソウル・シンガーとして呼ばれることに対し、反対を唱える気持ちはわかるが、結局は白人も黒人も同じだと思う。突き詰めれば音楽も似てくる。境を取り除くのはいいことだよ」
僕にはこの騒動が、87年8月末、本作より約2ヶ月早くリリースされた「キング・オブ・ポップ」マイケル・ジャクソンのアルバム《BAD》が、「黒人音楽」というカテゴライズを壊し、世界中のあらゆる人種に浸透していった現象と「対」をなしているように思われる。
ジェイムス・ブラウン、ビートルズやフレッド・アステアを愛したアフリカン・アメリカン、マイケル・ジャクソンが制作した《BAD》と、そのMJ や、プリンス、エルトン・ジョン、スティーヴィー・ワンダーに影響を受けたギリシャ系イギリス人、ジョージ・マイケルが制作した《FAITH》。この逆方向からジャンルを越境した2作は、共にアナログ・レコードからコンパクト・ディスクへとフォーマットの主流が変化する転換期の87年8月/10月に発売され、世界中で圧倒的な支持を受けた。しかし、そこには双方ともに超えなければいけない障壁が存在した・・・。
82年、くしくもデビュー曲「ワム!ラップ」で、当時まだ珍しい「白人ラッパー」としてデビューした「黒人音楽愛好家・実践家」であるジョージ・マイケルは、ワム!での活動と、さらに黒人音楽愛をオリジナルに純化させた《FAITH》によって、90年代以降のポップ・ミュージックの在り方を変えた。端的に言えば「黒人音楽のメインストリーム化」を白人側からのアプローチによって決定づけたのである。
再評価の時
「圧倒的な成功の代償」とまとめればシンプルに過ぎるが、この後90年代以降長きに渡って、アーティストとしてのジョージ・マイケルの「本質」に触れるメディア、音楽ジャーナリズムは非常に少なくなってしまった。確かに、90年に発表された次作、《リスン・ウィズアウト・プレジュディス Vol.1》以降、ジョージ自身がその暴走列車のような自らの成功曲線を意図的に終息させる方針をとったことや、レコード会社との裁判、私生活での逮捕・度重なるトラブルなど、伝説的アーティスト、マーヴィン・ゲイを彷彿させる天才特有の「波」があることが、その評価の難しさに大きな影響を与えていることも認めなければならない。極端な完璧主義者であり、寡作家なため、音楽的に新しいニュースを振りまき続けるわけでもない。
しかし、2010年代を迎え、80年代ポップ・ミュージックの「再評価」と、その実践が多くの若い世代のアーティストによって当たり前のように繰り返され「自然」なことになっている今、この丁寧にリマスタリングが施された記念盤が発売されることで、改めて偉大なアーティストであるジョージ・マイケルと、ポップ・ミュージックの魔法が詰まった《FAITH》にスポットが当たることは喜ばしいことだ。
「作曲という仕事にどういう魅力を感じますか?」という質問に、ジョージはこう答えている。
「自分に一番合ってると思ってるよ。歌手より作曲が向いてると・・・。現実的に考えてみると、思ったよりいい歌手になれたが、作曲家として功績を残したい。創造する仕事に生涯をかけた人なら、何かを残したいと思うはずだ。記憶をたどらなくても、皆が思い出せるような何かをね。僕は歌い継がれる歌を書く自信があるんだ」
2011年現在、新しいアルバムを制作している、という噂も聴こえてくるジョージ。
近年は残念ながらゴシップ絡みの報道が音楽家としてのニュースを上回ってしまっているジョージであるが、僕は特に我が国日本において、彼のシンガー、ソングライター、サウンドメイカー、プロデューサーとしての正当な評価が下される日が近いと信じている。
西寺郷太 NONA REEVES
(本稿は2011年2月に発売された『FAITH』デラックス・コレクターズ・エディションのライナーノーツを筆者の許可を得て転載したものです)