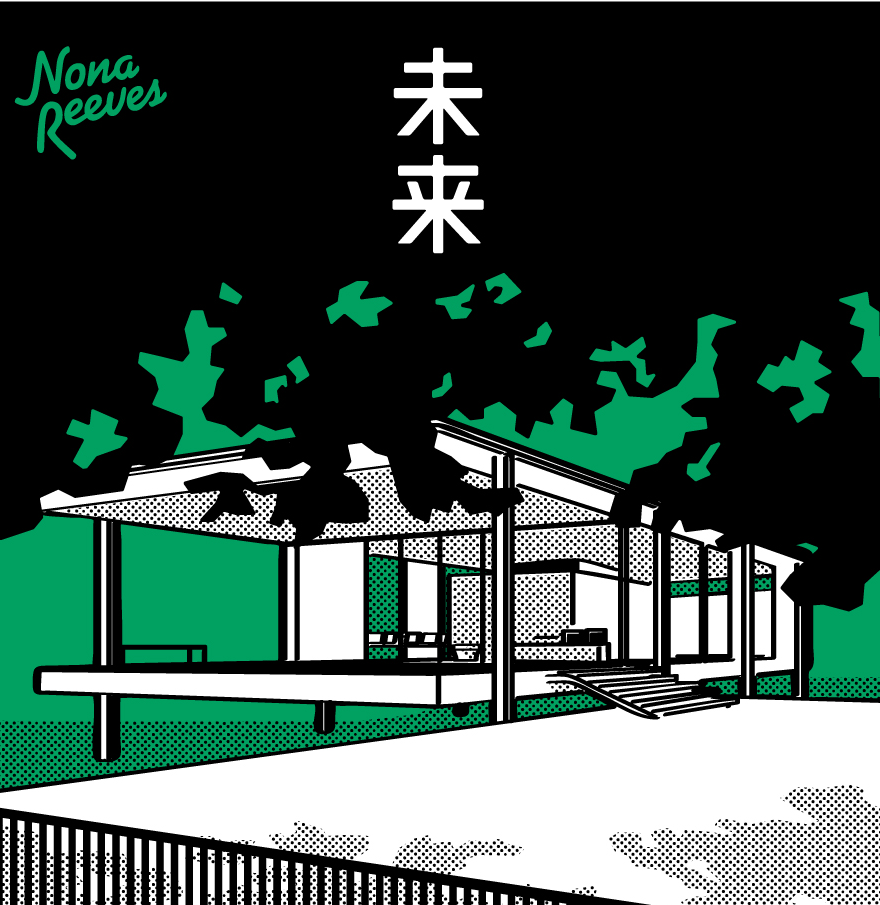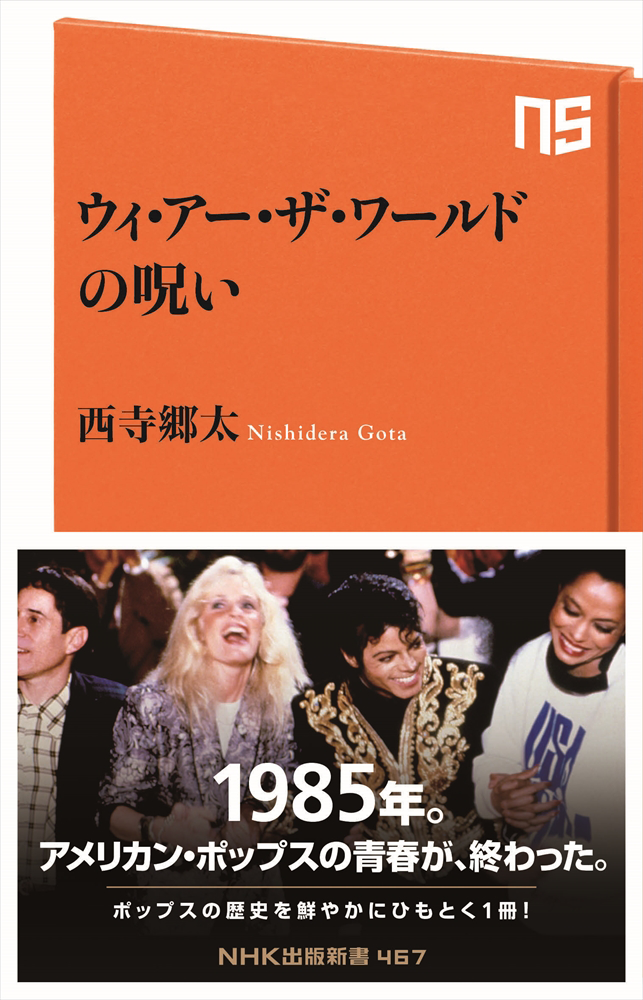西寺郷太 It's a Pops
NONA REEVES西寺郷太が洋楽ヒット曲の仕組みや背景を徹底分析する好評連載
第18回
プリンス「クリスタル・ボール」
(1986年)【前編】

―― 前回のボブ・ディランの同郷としてのミネソタ州、そしてテーマ曲だった「きみは大きな存在」の録音地ミネアポリス繋がりで、今回は約束どおりプリンスを取り上げてみたいと思います。今回は少し変則ながらも「SONY発」という連載ルールに当てはめ、昨年夏から始まった’95年以降に発表されたプリンス24タイトルのデジタル配信を対象とさせてもらいました。
西寺 数あるプリンス名曲の中から、’98年に発表された4枚組『クリスタル・ボール』からタイトル曲となる「クリスタル・ボール」を今回の連載テーマ曲とさせてもらいます。このアルバムは’86年から’96年の間に録音されたプリンスの……
―― あーちょっと待ってください! 本題に入る前に!! 連載でプリンスを取り上げることがあったら郷太さんに絶対に言いたいことが2つあったので、忘れないうちに最初に言っておいてもいいですか?
西寺 え、なんですか(笑)?
―― 郷太さんは著作『プリンス論』('15年)のなかで、こんなことを書いているんです。ここで読んでいいですか?
西寺 いつもですけど、凄い熱量ですね(笑)!
―― (中略)<「パープル・レイン」の凄まじいところは、サビ部分♪パープル・レイン、パープル・レイン~のヴォーカル部分を、プリンス以外のヴォーカルでも容易に置き換え可能なことだ。例えばアメリカを代表する白人ロックンローラー、ブルース・スプリングスティーンのしゃがれたシャウト声でもいい。ジョン・ボン・ジョヴィの甘くハスキー声でもいい。彼らが歌う「パープル・レイン」のサビを想像してほしい。その一方で、あまりにも黒人音楽的な特徴を備えた「ウォナ・ビー・ユア・ラヴァー」や「1999」を歌うブルース・スプリングスティーンやジョン・ボン・ジョヴィは全く想像もつかない。「パープル・レイン」こそ、プリンスがいかに作曲やアレンジの幅が広いアーティストであるかを証明する曲である。少年時代から“白”か“黒”かで音楽を区別して聴くことのなかった彼だからこそ可能な“マリアージュ”なのだ……>(『プリンス論』第2章「紫の革命」より)。
西寺 この「予言」は結果的に、残念な形でしたが当たりましたね……。

- 『プリンス論』
西寺郷太・著
2015年9月17日発売
新潮新書
―― 初版は'15年9月でした。プリンスが亡くなったのは7か月後の'16年4月21日。その2日後、ブルース・スプリングスティーン&Eストリート・バンドはNY公演のオープニングでいきなりプリンスを追悼して「パープル・レイン」を演奏したんです。郷太さんの指摘どおりというか、必然というか、鳥肌でした。‘84年の『パープル・レイン』『BORN IN THE U.S.A.』のライバル関係だった背景も重なって感動的なシーンでした。ちなみにこの追悼「パープル・レイン」がまた素晴らしい演奏でニルス・ロフグレンのギターは文字通り大泣き状態。ブルース熱唱も含めBOSSファンには早くも名演として語られています。
ボスとプリンスの関係:プリンス追悼「パープル・レイン」最新映像& 『BORN IN THE U.S.A.』と『パープル・レイン』の全米チャート・ヒストリーなど ブルース・スプリングスティーン日本公式サイト
西寺 結局、安川さんの好きなブルースの話(笑)。でも、プリンスはきちんと計画して'84年にアメリカでナンバーワンのミュージシャン、スーパースターになったと僕は思ってます。彼はそのためには、ファンク、ソウル、ダンスというカテゴリーだけじゃなく、アメリカの労働者、白人的な感性も飲み込んだ、ブルース・スプリングスティーンが歌ってもおかしくないアンセムを、作るべきだと判断したんじゃないかって。そんなプリンス自身の戦略を分析して『プリンス論』で述べたまでです。「黒人音楽のナンバーワン」じゃなくて、「アメリカのナンバーワン」「世界のナンバーワン」になるんだって。ご指摘とおりプリンスが亡くなった2日後にブルースが「パープル・レイン」で追悼したけれど、これが「ビートに抱かれて」とか「KISS」だったらありえないわけです。ファルセットの「KISS」を腰振りながら踊り歌うブルースは、ありえない。だけど「パープル・レイン」に関して言えば、ジョン・ボン・ジョヴィでもスティーヴン・タイラーでも、絶対にハマると僕は昔から思っていて、それを記したら結果的に予言になってしまったわけですね。それにしてもブルースのバージョンは、素晴らしかったですね。
―― あ、それから予言というか的中というか、『プリンス論』には全米チャート・マニアの僕としてはニヤリとする筆跡もありまして。
西寺 もしかして、プリンス「KISS」が全米1位、プリンスのクリストファー名義のバングルス=スザンナ・ホフスへの提供曲「マニック・マンデー」が全米2位の同週ワンツーフィニッシュのことだったり?
1986年4月19日付ビルボードHOT100チャート
―― はい……’86年4月19日付けビルボードHOT100でプリンス楽曲が1,2位独占なんですが、でももっと面白いのが、その前週までの首位がファルコの「ロック・ミー・アマデウス」だったんですよ。で、また『プリンス論』読みますよ。<10分28秒の大曲「クリスタル・ボール」こそが、プリンスの音楽キャリアの中で最も凄みのある傑作だと僕は信じて疑わない。スザンナのバックグラウンド・ヴォーカルとオーケストラ編曲のクレア・フィッシャーの参加を除く、すべての楽器を彼自身が手掛けている。まさに20世紀のヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトと言っていい、百年に一度の天才が刻みつけたタペストリーだ……>(『プリンス論』第3章「ペイズリーパーク王朝」より)。
西寺 アハハハ……アマデウス繋がりは偶然ですね(笑)。深読み過ぎ(笑)。チャートのマニア安川さんには著者の僕が意図していなかった景色が見えていたわけですね。そういった意味では、いま安川さんがきっと無意識で読み上げた文節も今日僕が話そうとしていたことと深く関係していますよ。今日僕が話そうとしている連載テーマ曲「クリスタル・ボール」、この曲がレコーディングされたのが、'86年4月17日。
The Bangles「Manic Monday」(1986)
―― あ、全米チャートのワンツーフィンッシュと同じ週だ。初めてチャート情報が有機的に繋がった予感(笑)。
西寺 でしょ(笑)。当時プリンスが住んでいたミネアポリス郊外の「チャンハッセン」、現地の発音を聞くと「チャナッセン」っていう人もいるんですけど、ギャルピン通りのホーム・スタジオでレコーディングされました。翌年に完成するペイズリー・パーク・スタジオの割とすぐそばです。この時期、まだプロトゥールズやロジックなどPCでのレコーディングは生まれてません。あくまでも彼自身の頭の中で、完成までの音像をプロセスの中で描きながらじゃないと、こういう曲は作れません。ある種の修行僧かってくらいのテンションで、ドラム、ギター、ベース、キーボード。ストリングスとコーラスを除いて、演奏は彼独り。ドラムソロとかもちょっとやばいんですよね。初めて聴いた時、現代のアマデウスはプリンスだと本当に思いましたよ(笑) 。全知全能感が半端ない。何分ありましたっけ?

- プリンス
『クリスタル・ボール』
(1998年)
2018年8月17日から配信済
sonymusic
―― 10分28秒のようです。
西寺 ポップ・フィールドでもナンバーワン、だけどアグレッシブでアバンギャルドな音楽性でも俺は天下一なんだ、思い知れっていう「凄み」を改めて感じますね。4か月後の8月4日、ハリウッドのオーシャン・ウェイ・スタジオで、僕自身がプリンスの歴史でも最強コンビのひとりと思っている作編曲家のクレア・フィッシャーにストリング・アレンジメントを含むオーケストラ録音をしてもらってます。コーラスは、当時彼女だったスザンヌ。
―― バングルスの。
西寺 あ(笑)。いや、スザンナ・ホフスじゃなくて、スザンナ・メルヴォワン。彼女は、ザ・レヴォリューションのギタリストのウェンディの双子の妹ですね。
―― 今日の今までプリンスにまつわる「スザンナ」はホフスだけだと思ってました(笑)。ところで、「クリスタル・ボール」は’86年の製作時期から見ればプリンス&ザ・レヴォリューション作品ということになるのですか?
西寺 本題ですね(ニヤリ)。『フォー・ユー』(’78年)でのデビュー以来、レコーディング作品に関して、一部の例外を除いて彼ひとりが演奏を担当していましたが、『パープル・レイン』(’84年)で正式にザ・レヴォリューション名義となって、アルバムの半数程度はバンドでレコーディングもするスタイルに変わっていくんです。ヴォーカル・スタイルの変更も大きかったですね。

- プリンス
『1999』
(1982年)
ワーナーミュージック・ジャパン
プリンスがビッグになればなるほど演奏する場所がライヴハウスからスケートリンク、コンサートホールなど大きくなっていきます。そうすると『プリンス論』にも書きましたが、彼の初期代名詞でもあるファルセット・ヴォイスが広い会場になればなるほど届きにくいんですね。ドラムや楽器が爆音で演奏されるライヴのステージでは、裏声がマイクで拾いにくいんですよ。今はイヤモニもありますし、モニター環境がまだ快適になってますけど、当時は音響の限界がありましたし。マイクに向かって歌ってたファルセットを、聞こえないからって感度を上げちゃうと、今度は「キーン!」ってハウっちゃうんですよ。で、地声でも歌わないとって方針転換したのが、プリンス初の全米トップ10ヒットとなった「リトル・レッド・コルヴェット」(’83年5月全米6位)です。あの囁くような、喉をクイッて鳴らすような悪戯っぽい声です。『1999』に関しては、プリンス&ザ・レヴォリューションて小っちゃく手描きでは書いてはあるんですけど、名義は「プリンス」。
―― プリンス&ザ・レヴォリューション名義は……。
西寺 アルバムで言えば『パープル・レイン』(’84年)に始まって、『アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ』(’85年)『パレード』(’86年)の3枚ですね。その次に“幻”となってしまったバンドとの共同制作アルバム『ドリーム・ファクトリー』のために作った曲がたくさんありまして、その中の一曲が「クリスタル・ボール」です。理由はもちろん諸説ありますが、この後、リサ、ウェンディ、ボビー・Zらザ・レヴォリューションのメンバーにもう君たちとはやらないって宣言して。で、彼がシーラ・E.と密接に関わりつつ、個人の作品として結実させたのが2枚組『サイン・オブ・ザ・タイムス』(’87年)。

- プリンス&ザ・レヴォリューション
『パープル・レイン』
(1984年)
ワーナーミュージック・ジャパン

- プリンス&ザ・レヴォリューション
『アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ』
(1985年)
ワーナーミュージック・ジャパン
―― それが、あの『パレード』ワールド・ツアー最終公演=’86年9月9日・横浜スタジアムでのザ・レヴォリューション解散に繋がっていくわけですね。
西寺 ザ・レヴォリューションのポイントとしては重要なのが、リサとウェンディの存在。両方ともお父さんが超スーパーなセッション・ミュージシャンで。リサの父親ゲイリー・L・コールマンは、凄腕職人集団レッキング・クルーに属し、サイモン&ガーファンクル『明日に架ける橋』にも参加してるパーカッショニスト。ウェンディの父親マイクはジャズ・ピアニストでフランク・シナトラ、ジョン・レノン、ジャクソン5の「ABC」、ビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』でも弾いてます。このお父さん同士が仲良かったんですよね、で、リサとウェンディは小っちゃい頃から音楽教育を受けていて。対してプリンスは、ミネアポリスで叩き上げの独学なんですよ。確かにプリンスのお父さん、ジョン・L・ネルソンもジャズ・ピアニストでしたし、僕は最近、発売されたジョン・Lの作品聴いて感動しまして。めちゃくちゃ才能ある人だったんだな、と。ただ、プリンスの父ジョンは昼間は収入を確保するために普通に会社で働いて、夜、白人相手にラウンジでピアノを弾くような、そういう暮らしの「ミュージシャン」。華々しくヒット・レコードに関わり、音楽家として知名度も信頼も頂点を極めるリサやウェンディのパパ達とは全く違います。リサとウェンディは、環境に恵まれポップスやロックだけでなく、ジャズやクラシックの感覚も持つ才女達でした。それがもしも同性だったら、プリンスも認めたくなかったんじゃないかなって。でもリサとウェンディは、都会っ子で、若くてヴィジュアル的にもインパクトのある女子コンビだった。メンバーに加えてみたら、コードに関しても、アレンジに関してもめっちゃ良いアイディア出してくれる。サンキュー! サンキュー!! という感じだったんじゃないですかね、最初は……。僕はアルバム『パレード』が大好きなんですけど、最後12曲目に「スノウ・イン・エイプリル」って曲が収録されています。ディアンジェロもカヴァーしている大好きなバラードなんですが、あの曲は基本的には、リサとウェンディが作曲で、プリンスが作詞って言われてるんですよね。

- プリンス&ザ・レヴォリューション
『パレード』
(1986年)
ワーナーミュージック・ジャパン
―― この頃は本当に共作していたんですね。
西寺 「パープル・レイン」のイントロのコードも、プリンスが作ったコードをウェンディが自分でギターを弾いてこんな風に変えたって後にドキュメンタリーで説明していますよ。その事実も含めて、ブルース・スプリングスティーンがカヴァーしてもおかしくなかったっていうところにも繋がっていくんです。白人のコード感覚が入っているんですよ。で、この話は先ほど話したアレンジャーのクレア・フィッシャーに会ってないってエピソードにもつながるというか。こここそが僕はプリンスというアーティストを理解する鍵のひとつじゃないかな、と思っているんですけど。ディアンジェロの『ブラック・メサイア』(’15年)でストリングス関連を担当している、クレアの息子で愛弟子のブレント・フィッシャーがこう証言してるんです。
―― え? クレアの息子さんも音楽家なんですか? で、ディアンジェロに関わっている?
西寺 そうなんです。ブレントのキャリアは父親クレア・フィッシャーの助手として始まっているんですけどね。彼が言うにはプリンスは父クレアに一度も会いに来なかったと。
―― 一度も?
西寺 完璧主義で知られるプリンス、ワーカホリックでこだわり深いプリンスがオーケストラ・ダビングに一度も立ち会ってない、アイディアも全部お任せだったと。この証言がちょっと引っかかるんですよね。なぜなら特にアルバム『パレード』でクレア・フィッシャーが施したクールでエレガント、かつエキセントリックなストリングス・アレンジこそが「プリンスって凄いな、とんでもないな」っていう評価の決定打となった部分も大きいと思うからです。特に僕はそうでしたね。『パレード』の一曲目、「クリストファー・トレイシーのパレード」のイントロとかね。で、僕自身何度も自分の書いた曲にオーケストラ・ダビングしてもらってますけど、できる限り立ち会ってるんです。
―― そうなんですか! 普通は立ち会うんですかね?
西寺 いや、もちろん作曲家、プロデューサーによってまちまちだとは思うんですけど。ただ、僕の場合は憧れていた伝説のアレンジャー、例えば萩田光雄さん、服部隆之さん、筒美京平さん、山本拓夫さんなどこれまでたくさん自分の楽曲に参加してもらいましたが。
―― ちょっと聞くだけで、錚々たる面々ですね。
西寺 そうなんですよ(笑)。バンドマン上がりの僕にとって、特に畑違いのストリングスやブラスに関しては先輩方の魔法を体感させてもらうことが最大の勉強で。質問してみたり、ニュアンスを感じたり、大興奮の経験だったんで、できるだけ現場にいたいなと……。オーケストラのダビングやアレンジって、やっぱり考え方がぶつかる部分ですからね。音を加えてゴージャスにすればいいってもんでもないですから。
―― やっぱりデリケートなものなんですね。
西寺 それなのに、プリンスは'12年に亡くなった「長年の相棒」クレア・フィッシャーと一度も会わなかった。これは、結局プリンスの「クレアの仕事は尊敬するけど会いたくない」という意思だったんじゃないかな、と。クレア・フィッシャーは、ドナルド・バード、ディジー・ガレスピーらジャズ・レジェンドと仕事をして、ハービー・ハンコックまでが「自分のハーモニー感に多大な影響を与えてくれた恩人、彼がいなければ、今の私はいない」とまで言い切る天才です。ジャクソンズのアルバム『デスティニー』で、僕が愛してやまない「プッシュ・ミー・アウェイ」の神懸かったストリングス・アレンジメントもクレア。ま、「餅は餅屋で任せた」と言うと、そうなんでしょうけど。
―― 任せた?
西寺 うーん。『クリスタル・ボール』や『ドリーム・ファクトリー』が結局オクラ入りになり、ザ・レヴォリューションを解散しなければいけなかった理由。それは、クレア・フィッシャーやリサ、ウェンディのアイデアはめちゃくちゃ最高で研ぎ澄まされているから故に、プリンス自身が作りたい、作れる音楽そのものの純粋性を脅かしたからじゃないかなと。クレアに会ってしまうと、彼に共鳴し、その才能に持っていかれ過ぎるかも、それを警戒したんじゃないかな?って、ちょっと思うんですよね。
―― 彼らには「才能がありすぎ」た、というわけですか?
西寺 その後のプリンスの選んだ道を考えると、僕はそう感じてしまうんですよね。より「精神的」で「ピュア」な音楽へと向き合ってゆく。元々、ひとりですべての演奏をこなして、自宅録音の究極形のような人だったわけじゃないですか、プリンスって。それがどんどん増殖するようにパートナーが増えた。それはひとつの作戦だった。しかし、80年代中期の「白人や日本人のロック・ファン」がプリンスに心酔した最大のポイントは、プリンス+リサ+ウェンディ+クレア・フィッシャーの融合だったのでは?と。え! 何? プリンス、おかしくない? この人!? って思った時、一瞬、十代の僕はその響きの全てをプリンスがコントロールし生み出していると思った。
―― 『パープル・レイン』からしばらくの間、プリンスにシビれた人が、今回の連載対象となる’95年以降の彼の音楽に何かが見えないって言う場面に出くわすことも多いようなのですが。僕自身がそうかもしれません。
西寺 いや、先ほど言ったように、むしろあの時代はプリンスというアーティストが自伝的映画の主演も含め、計算して生み出した特殊な乱反射。むしろ、’95年以降がプリンスの「真髄」じゃないかなって思ってるんです。プリンスのキャリアをポール・マッカートニーに重ねれば「ザ・レヴォリューション」がビートルズ、「ニュー・パワー・ジェネレーション」がウイングス、そしてその後がポールのソロ、みたいな時代分けなんですよ、僕的には。それくらい「ザ・レヴォリューション」期、そして特に『パレード』でのクレア・フィッシャーとのタッグはジョンとポール、ジョージ、リンゴにプロデューサーにジョージ・マーティンなど個性が激突した「バンド」だったんだよ、と。

- プリンス&ザ・レヴォリューション(1984年)
写真提供:ワーナーミュージック・ジャパン
―― 『パープル・レイン』こそがプリンス! とずっとさっきまで口にしていた自分がなんだか……。
西寺 良い悪い、高い低いの問題じゃないですから。プリンスの立場からすれば、白人も含んだアメリカや世界で天下を獲った、イエイ、いやでも満足できない。結局、ザ・レヴォリューションでクリエイトした音楽が「俺」って賞賛されるけど、やっぱり俺の100%の音楽じゃねーじゃん。ちょっと違うんだよなって。結局、これだけぶっとんだ「クリスタル・ボール」をお蔵入りにして、全部一人きりで音世界を完結させたシングル「サイン・オブ・ザ・タイムス」の道を彼は選んだんです。それで言えば、'89年にリリースされた『バットマン』のサウンドトラックは、さらにその道を研ぎ澄ましたと僕は思ってます。映画のサントラなんで一瞬受取る側はブレたんですが、あのアルバムは相当ピュアだな、と。「脱レヴォリューション」の完成。天下統一前に世に問うた'81年『戦慄の貴公子』への8年経った回答であり、原点回帰って感じがするんですよね。一曲目の「CONTROVERSY」と「ザ・フューチャー」、「ドゥ・ミー・ベイビー」と「スキャンダラス」も形を少しずつ変貌させながらかなり呼応してる気がします。プリンスにしてみれば、バンドの時期は「プリンス&ザ・レヴォリューション」ってちゃんと名乗ってたやん、って気持ちもあったと思いますけどね。
―― 「俺ひとりじゃないよ」って公言したってことですかね?
西寺 はい。世間一般から見たら「ザ・レヴォリューション」ってプリンスとその他、って感じに捉えたかもしれないけれど、じつはすごくフェアな表記で。
―― 「ザ・レヴォリューション」も重要だよ、と。
西寺 この「クリスタル・ボール」の曲に関しても、演奏はひとりでやっているけれど、クレア・フィッシャーやウェンディの双子の妹スザンヌが入ってる時点で、やっぱり気持ちは「ザ・レヴォリューション」的だったのかなって。結局、お蔵入りしてブートレグで出回っていた楽曲「クリスタル・ボール」が12年後、公の場に正式に登場するわけですが、僕はこのタイミングにも深い意味があったと思っています。
[後編]に続く
聞き手/安川達也(otonano編集部)

- 「Crystal Ball」PRINCE(1986)
Recorded:1986
Release:January 29, 1998.
Songwriter:Prince
Produce:Prince
Label:NPG
'86年から'96年の約10年間の未発表曲を中心に構成され、'98年に発表した4枚組アルバム『クリスタル・ボール』のタイトル曲。'98年発表当時は5枚組という歴史的作品でもあった。商業的なレコード業界では遅めのテンポでしか作品を発表できないことを長年嘆いていた彼にとって、遂に好きなだけ音楽をファンとシェア、かつ彼の望むスピーディーなテンポで発表できた作品といえる。彼はネットを通じて全世界のファンがどれがけ興味を示しているか正確に把握、その結果『クリスタル・ボール』という3枚組のほか、アコースティック作品集の『ザ・トゥルース』、さらにインストゥルメンタル盤『カーマストラ』も付いてくるという前代未聞の特別仕様だった(この計5枚組の仕様は事前に電話予約した場合のみ手に入れられたもので、一般流通の際は4枚組に縮小されていた)。オープニングを飾る10分を超えるタイトル曲「クリスタル・ボール」は’86年に制作されている。